今回は最近注目を集めている「古民家リフォーム・リノベーション」についてお話します。
昔ながらの日本家屋を利用し、時代に合わせた空間デザインを施したり、住居としての機能を高めたりできるのが、古民家リフォーム・リノベーションの魅力です。
レトロモダンな雰囲気やデザイン性の高さに日本人ならではの魅力を感じる人も多いと思いますが、実際にどんな住み心地なのか、リフォームをする際は何を注意すればいいのか気になりますよね。
古民家リノベーションの魅力や注意点、費用、補助金などについてご紹介します。
古民家ならではのメリット・デメリットについても解説しますので、参考にしてください。
 【外壁アドバイザー】大屋敷竜二
【外壁アドバイザー】大屋敷竜二
塗装職人歴28年。中学卒業後、塗装業界に入り様々な会社で経験を積む。 塗装以外にも多能工として現在も修業中。
◎主に参加していた有名な現場:TDL・東京タワー・有名宿泊施設・戸建て・マンション等
Contents
リフォームとリノベーションの違いとは?

古い日本家屋には現代的な家にはない、趣や雰囲気がありますよね。
そんな昔ながらの日本家屋に手を加え、古い趣や雰囲気を大事にしたまま住みやすい家へと改修することをリフォームやリノベーションと言います。
リフォームとリノベーションの言葉の定義に違いはありません。

古民家リフォームのメリット

日本人であるなら縁の深い古民家。その古民家を文化として技術として残していく事も大切だと思います。
古くからある日本家屋は落ち着きますし、魅力たっぷりな古民家を改めて紹介します。
趣がある

古民家をリフォームして住みたいと思う人の多くは、古民家の趣や雰囲気が好きだと感じているのも一つの理由でしょう。
古い日本家屋の独特な質感や、土間・縁側といった現代の一般住宅ではほとんど見ることのできない空間をそのまま活かすことで、昔の暮らしを踏襲しつつ自分らしい暮らしができ、居心地の良い空間になるでしょう。
古民家の場合、柱や梁など、元々の素材が露出していることが多いので、リフォームをする場合はそれらをそのまま活かすような、間取りや内装の仕上げをすることが多く、また、それが出来るのは古民家のみです。
新築の場合は成形された木材などが使われているのですが、古民家の場合、柱や梁の建材が自然そのままで曲がっていたり、ごつごつしていたりします。
大部分を新しくする場合でも、古い部分をあえて残すことで、新しさと古さの落差をデザインの中に生み出すこともできます。

今日は天王寺の「菜乃庵」さんでお昼ごはん。一汁八菜の農家ごはんは、いろんな野菜のおそうざいが、優しくも凛とした味付けなので、十分に満足できます。お店は築100年の古民家で、風流なお庭をぼーっと眺めながらゆったりと過ごせます。カラダとココロに栄養がほしいときにおすすめです。#わびごはん pic.twitter.com/rXouanHerY
— わび (@Japanese_hare) March 30, 2023

流行に左右されにくい

家のデザインにも流行り廃りがあり、外壁を塗装してイメージチェンジや流行色に乗ったりしますが、古民家のたたずまいには流行にとらわれないならではの魅力があります。
新しいものは古くなります。トレンドを求めると、いずれ流行遅れになりますが、古民家はもともと古いものなので、逆に言えば流行から取り残されるということがそもそもありません。
古さの中に不思議な魅力がある古民家リフォームは流行に左右されないという良さがあります。
また、ヒノキやケヤキなど、立派な建材などが柱や梁に使われている、しっかりとしたつくりの建物が多いのも古民家の特徴の一つ。今ではもう手に入らないような建材もありますし、歴史のある建物を活かすことは、資源の保護という観点からも注目したいポイントでもあります。
建物の質が良ければ、わざわざ建て替えをする必要はありませんし、建て替えではなく、リフォームすることで、風土に合った佇まいの建物を残せるというのはとどのつまり省エネにもなります。
強度があり、資源保護にもなる

古民家の柱や梁といった材料には、ヒノキやケヤキなどが使われています。
強度が落ちるまでに、ヒノキは1200年、ケヤキは800年ほどと言われており、そのため古民家は、基礎の土台がしっかりした建造物と言えます。
また、現在ではこのような古民家の柱や梁はかなり入手困難なため、歴史ある建物や建材をそのまま残すことが資源の保護にも繋がります。
固定資産税が軽減できる

固定資産税は、築年数により税額が決まるため、既存の家をリフォームすると、新築に建て替えることに比べて税金を軽減できるというメリットがあります。
一方で、日本家屋特有の吹抜けをなくして2階建て等に改築して延べ床面積を増やすなど、固定資産税が高くなるリフォームもあります。固定資産税を確実に抑えたい方は、注意が必要です。
さらには、自治体によって、固定資産税の解釈は細かく異なるため、増築したい場合には注意が必要です。
特に築年数の古い住宅は、増築の許可自体が下りないことも多いです。
まずは増築を行う前に、該当する自治体の窓口で相談してみてください。
なお、増築せずに部屋を増やしたい場合は、間取り変更リフォームを検討することをおすすめします。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産にかかる税金のことを言います。固定資産税は固定資産税課税評価額によって決まりますが築年数が25年以上経っている建物については経年原価補正が行われ、減額が見込まれます。
古民家リフォームのデメリット

一見メリットが多く魅力的な古民家リフォームですが、デメリットがあるのも事実です。
耐震性に不安

昔から地震が多かった日本の家屋は、あえて壁や柱や梁の接合部分を変形させて、地震の時に全体にかかる揺れを吸収できるように造られています。
しかし、古民家が建てられた時と、現在とでは、住宅の耐震基準が大きく異なります。
また建築物は、目には見えないところが劣化・破損している場合もあります。
可能であれば住宅診断を受け、建物の状態に合わせて補強工事を行いましょう。
断熱性に難あり

古民家は、冷蔵・冷凍の設備が発達していない頃の建物なので、風通しを考慮した造りとなっています。
現代の住まいと違って、天井が高いのも特徴です。
夏は快適に過ごせますが、冬場は暖房費のコストがかさんでしまいます。
リフォーム工事の際に、断熱材導入の予算なども考えておいたほうが良いかもしれません。
リフォームの範囲が建物の一部の場合、住まい全体の耐震補強を行うことは難しくなることもありますが、断熱性を高める工事は、部分的なリフォームの場合でも希望の箇所に施工することが可能です。
古民家の場合、壁の内側に空間がなく、一般的な木造住宅で用いるような板状の断熱材を使用できないケースもありますが、そのような場合は非常に薄いシート状の断熱材などを用いて対応することもあります。
予想していたよりもリフォーム費用がかかる

建て替えや新築に比べてコストがかかりにくいというメリットがある反面、予想していたよりも工事費用が必要になってしまう傾向があることも、古民家リフォームの注意点です。
希少価値のある材料が使われているという魅力がありますが、同じような材料にこだわりだしてしまうとあっというまに高額になってしまいます。
特に構造部分も工事をする必要がある場合や、リフォームをする範囲が広い時は、廃材処分費もかさんでしまいます。

高齢の方が暮らす場合には、現在の建物よりは親切設計ではない為、バリアフリー工事が必要になることも多いです。
リフォームをして古民家に住むためには、計画的に余裕を持って予算を組むように心がけましょう。
古民家リフォームの費用・相場は?

以上のメリット・デメリットを踏まえて、具体的に検討すべき工事について、詳しくご説明していきます。
リフォーム費用は施工の内容や広さなどによってさまざまなので、一概には言えませんが、例えば、設備の交換や内装のデザイン変更程度の内容であれば、300万円程の予算で行うこともあります。
古民家ならではのデザインに興味を持って、新たに古民家を購入し、自分たちが住むためにリフォームを行うような場合は、1000万円以内の予算でリフォームを検討する人も多いようです。
一方で、古民家を受け継いで、家を残していくために、建物全体の大掛かりなリフォームを行いたいというケースも少なくありません。
そのような場合は施工の範囲が広くなるので、費用が数千万円とかかることも珍しくありません。予算を重視するのか、建物の品質を保ちたいかなど、住む人の希望によってリノベーション費用の目安も変わってきます。
古民家のリフォームの際、必要になりやすい工事と費用目安は、以下の通りです。
| 耐震リフォーム | 30~200万円 |
| 断熱リフォーム | 5,000~3万円/㎡ |
| 暖房機器の導入 | 床暖房3~8万円/㎡ (温水式の場合+25~100万円で熱源機設置が必要) |
| 屋根のリフォーム | 20~300万円 |
| 外壁のリフォーム | 50~400万円 |
| 水回りリフォーム 【キッチン・浴室・洗面所・トイレ】 | キッチン 50~150万円 浴室 100~150万円 洗面所 20~50万円 トイレ 20~50万円 |
| 間取り変更 | 20~400万円 |
| バリアフリー 【手摺設置・段差解消】 | 手摺設置 5000~15万円/箇所 段差解消 1~50万円/箇所 |
優先的にリフォームしたい内容を整理した上で、費用対策を考える事が大切です。
既存の柱や梁など、そのまま活かせる物はなるべく残したりすることも、施工費を抑えるためには重要です。
リフォーム会社の提案やご自身の希望と合わせて上記の表をチェックしながら、住まいに必要な工事・不要な工事を見極め、予算に合わせてリフォームプランを決定していきましょう。
最新のキッチンや壁・床・建具などの建材を、ご自分の好みだけで選んでしまうと、古民家ならではの古い趣きとうまく調和せず、ちぐはぐな印象になってしまい取り返しがつかなくなってしまうことも…。
デザイン面からしっかりプランニングしてもらえるリフォーム会社に依頼し、相談しながら進めましょう。
古民家リフォームは、基礎や耐震補強、断熱工事を行ったり、既存を活かしながら最新設備を設置するなど、知識やプランニング力が必要になります。
補助金制度について

古民家リフォームには、主に次の3種類の補助金制度が利用できます。
耐震補強の為の補助金
耐震補強を実施する場合も、自治体によっては補助金がもらえることがあります。
例えば、長野県佐久市では木造住宅の耐震補強工事を行う場合に耐震補強工事と耐震改修促進リフォーム工事の合計で130万円の補助金を支給しています。
1981年5月31日以前に木造在来工法で建てられた住宅が対象です。
断熱性能向上リフォームも合わせて実施すれば、さらに30万円を上限に追加して最大160万円の補助が受けられます。
また、東京都中野区も、1981年5月31日以前に木造在来工法で建てられた2階建て以下の住宅を対象に助成金制度があります。
助成金額は助成対象経費の2分の1で、最大150万円です。
古民家リフォームにあたって、耐震補強は必要なケースが多い工事です。
お住まいの自治体の制度を調べて、補助金が利用できるか確認してみてください。
バリアフリー化の為の補助金
自治体によって、バリアフリー化を促進する独自の補助金制度があります。
例えば東京都の一部ではおおむね65歳以上で、住宅の改修が必要な人を対象に住宅改修費用を負担しています。
上限は20万円で、床材の変更や扉の取り替え、浴槽の取り替えなどの改修が対象です。
また、大阪市で対象になるのは介護保険料段階が第1~6段階であり、要介護認定で要支援以上の認定を受けた高齢者のいる世帯です。
介護保険制度の住宅改修と同時に行われる関連工事に対して、第1~4段階は最大30万円、第5~6段階は最大5万円が助成されます。
古民家リフォームにあたりバリアフリー化も実施したい場合は、地域の補助金を調べて見る事をおすすめします。
自治体独自の補助金
古民家の再生を対象に、自治体独自の補助金を支給しているケースもあります。
例えば兵庫県の「古民家再生促進支援事業」を例に挙げると、地域活動や交流の拠点、宿泊体験施設など地域の活性化につながる古民家再生に補助金を支給しています。
築50年以上経過しており、伝統的木造建築技術で建築されている古民家や歴史的建築物が対象です。
一般的な古民家であれば最大500万円、歴史的建築物であれば最大1,000万円まで補助が受け取れます。
地域によってさまざまな補助金制度があるので、お住まいの役所の窓口で確認してみてください。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
古民家に住み続けるにはリフォームが必要になってきます。
ですが現代の建物とは違った形での問題が色々とあります。
日本の文化遺産としても大切な古民家ですし和の心を忘れない為にも残していけたらいいですね。








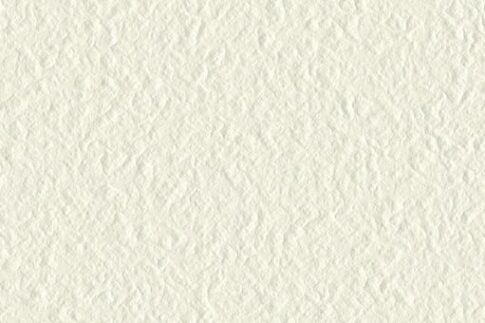


コメントを残す